2025年で16回目の挑戦となる「ニュルブルクリンク24時間レース」にSUBARU/STIはWRX S4をベースにした「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2025」(ゼッケン88番)で参戦した。6月22日(日)の午後4時。SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2025がチェッカーを受けるとチームメンバーは目に涙を浮かべて抱き合い称えあった。

2008年から始まったニュルブルクリンク24時間レースへの挑戦は「教科書を疑え」をキーに車両開発を行ない、これまでの常識の数々を覆してきた。STIの挑戦による功績は、後付けできるアフターパーツへの展開、S210で代表されるコンプリートカーの製作、そしてSUBARUのカタログモデルへのフィードバックなど、スバルの最先端を突き進む挑戦でもあった。
そのリーダー辰己英治が2024年に勇退し、後継者たちに引き継がれた。まとめ役の沢田拓也、宮沢竜太、渋谷直樹にとって辰己抜きのニュル24hは初挑戦であり、そこで起きた2025年のレースは、厳しい試練を受けることとなった。

2025年の参戦マシンとは
参戦マシンはWRX S4をベースとした2024年マシンの改良型だ。じつは2024年のレースは濃霧に覆われ、実質7時間しか走行できず、マシン能力を存分に発揮するには至らなかったレースでもあった。

沢田監督は2025年に向けて、さらにレベルアップする改良を2024年参戦マシンに施し、16回目の挑戦を迎えていた。開発のドライバーには前年に続いて、経験豊富な佐々木孝太と昨年からのドライバーである久保凜太郎を迎えて開発を進めている。2024年からの変更点、進化点については、こちらの記事で詳細をお伝えしているので、参考にしていただきたい。
関連記事:SUBARU/STI 16回目の挑戦 WRX S4でニュルブルクリンク24時間レースSP4Tクラスに参戦
概要を説明すると燃費を良くする工夫とハンドリング性能の向上という2つのテーマをキーとして開発している。エンジン本体はエアリストリクターの口径を広げ吸気量を増やしている。それを出力アップではなく、燃費改善に使う方向でチューニングがなされている。そして空力性能をチューニングし、ハイスピード時のコーナリンググリップを上げ、旋回速度を上げる方向でマシンを仕上げていた。



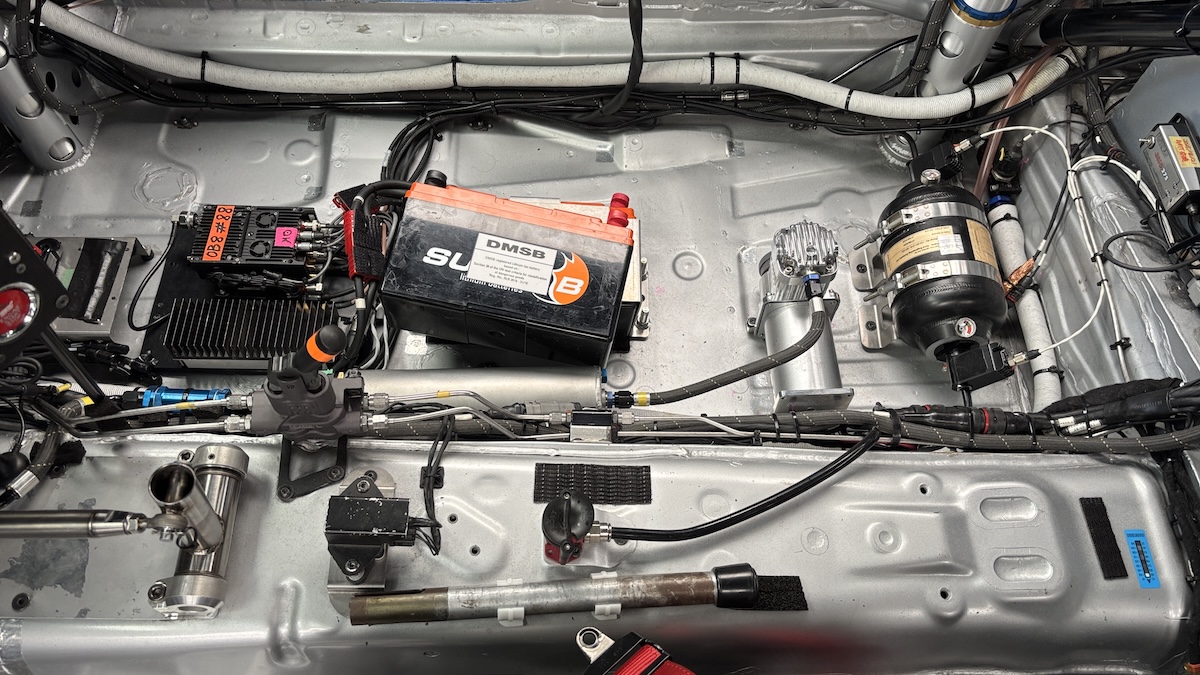
滑り出しは順調なNBR
ニュル24hレースの前哨戦、通称「QFレース」は、本番レースの約2ヶ月前に2レースが行なわれ、開発ドライバーのひとり久保凜太郎とティム・シュリックのコンビで2レースともクラス優勝を飾っている。その2レースは雨とドライの両方の状況の中での優勝であり、2025年参戦マシンのレベルの高さを証明していた。

沢田監督は「24年マシンのエンジンやサスペンションのエイジングが未完でしたので、QFレースでは、そのあたりの確認もありました。ですからQFレースを終えた後に、主要部品のエンジン、サスペンション、ミッションなど全てを載せ替えています。ですから、本番レース最初の予選では、ハードパーツにアタリをつけて、かつ、QFの時と同じコンディションなのかのチェックを行ないます。ドライバーはQFレースを走り、開発に携わっている久保にやってもらいます。久保は24年のレースでもタイムと燃費のバランスが一番良かったんですよね」

6月19日木曜日。ニュル24hには公式練習やフリー走行といった走行枠はなく、いきなり予選から始まる。木曜の午後に120分の予選があり、同日の夜20時15分から23時30分まで195分間の予選2回目がある。

2024年は8分52秒台の予選タイムだったが、QF レースでは8分50秒台にアップしている。これがSTIが作ったSUBARU WRX NBR CHALLENGE 2025というわけだ。ただ、2025年のレースは6月中旬開催で、欧州の夏真っ盛りの開催。だから気温、路面温度も高く、つまりは充填効率も良いわけではなく、ターボ車のWRX がベストラップを更新できる期待は薄らいでいるのが現実だった。
冬場に行なわれたシェイクダウン・テストのとき、沢田監督は目標として145周の最多ラップの更新と1周8分48秒台を掲げていた。しかし実際に現地に来てみると肌で感じる「夏」はマシンにとっては厳しい環境であることを感じていたのだ。
凜太郎はブレーキの焼き入れも含め、マシンのバランス、状態をチェックしながら予選を走った。タイムは余裕を持った走りで9分11秒台で周回し2ラップ計測の義務を消化した。

想定外のパーコレーション
予選1回目の時、凜太郎、ティム・シュリック、カルロ・ヴァン・ダムの3人が2ラップ計測の義務消化をする予定だった。しかし、凜太郎の走行後、ティムがピットアウトをしたが、エンジンが吹け上がらない現象が出た。メカニックは原因を探るものの、これといった明確な理由が見つからない。予選時間は刻々と過ぎていく。
エンジンエンジニアの菊地は燃料に問題があることを原因と考え、新たにガソリンを給油してみる。すると調子が戻り、ティムは無事に2周計測をして戻ってきた。だが予選時間終了が近づき、カルロはアウトラップとその翌ラップしか計測できておらず、2ラップ計測の義務消化はクリアできなかった。
さて、5時間15分後に始まる予選2回目に向けて、エンジンが吹け上がらない原因を解明せねばならなかった。菊地の予想ではパーコレーションを考えていた。気温の上昇で燃料内に気泡が発生してしまう現象だ。2024年の夏、SUGOでテストを行なった時に、そうした現象は一度も起きていない。しかし菊地は燃料の質には違いがあり、アルコール分が多いと蒸発しやすく気泡が発生しやすいというのだ。
そこでメカニックたちは急遽燃料の通り道を冷やすことを考え、風を当てたり、熱源自体を遮熱剤で覆うなどの対策を行なった。
予選2回目でカルロがベストラップ
予選2回目。カルロが本気のタイムアタックを開始する。沢田監督は、午後8時15分の予選開始時刻は昼間同然の明るさがあり、気温や路温も下がり始めるので、タイムは出しやすいと言う。ちなみに夏至のころのニュルは午後9時過ぎが日の入りだ。

カルロは計測2周目に8分56秒879を出し、ピットに戻った。続いて孝太のアタックは夕暮れ時であり、見ずらい時間帯。しかもダブルイエローが多く佐々木のベストは9分04秒089だった。
6月20日金曜日は午後4時15分から5時45分までの90分間、最後の予選、3回目がある。チームによってはここをスキップするチームもある。チームは凜太郎がニュータイヤでのタイムアタックをしていないこともあり、この3回目を走ることにした。またパーコレーションの現象は、前日予選が夜間であり、気泡が発生しにくい状況でもあった。そのため、この3回目の予選で気泡の発生確認もする必要があった。
孝太がベストラップを計測
果たして本当に燃料の問題だったのか。明確な結論を持たないままの熱対策だったため、チームにとってはドキドキする重要な予選3回目となった。
まず、凜太郎がニュータイヤを装着して走行する。計測2周のうちイエローが全くないクリアな状態はなく、凜太郎は9分3秒140がベストとなった。一方、燃料の問題は起きていない。次に孝太が予選アタックをする。計測2周目に8分56秒629を出した。カルロより0.25秒速くチームトップタイムをマークした。25km以上走行して0.25秒差。改めてレーシングドライバーの凄さを感じさせる瞬間でもあった。そして燃料の問題も解決と判断した。
最速タイムは孝太がマークしたものの、じつはカルロはほとんど走っていないのだ。24年のレースが終わってから、次にSUBARU WRX NBR CHALLENGE 2025に乗ったのはこの予選2回目のアウトインを含めた3ラップだけなのだ。たったそれだけで一時はチームトップタイムを出すのだから恐れ入る。チームの予選順位は総合134台中54位だった。


前代未聞の赤旗中断
快晴の下、決勝レースは午後4時ちょうどにグループ1がローリングスタートを切った。88号車はグループ3でその十数分後にスタート。気温28度、路面温度46度。スタートドライバーを務めたのは孝太だ。レース後孝太は「ポールからのスタートだったので、2周目にファステストを狙ってました。だけど、すぐにダブルイエローがでてタイムは出せなかったのが残念」と話すように全てが88号車にとって順調のようだ。孝太はダブルイエロー(60km/h規制)の中9分12秒716で2周目を回ってきていた。

レースは8ラップ運用で、状況次第で9周の運用を投入する。145周最多周回数を超える挑戦が始まった。孝太の8周を終え2番手は凜太郎だ。凜太郎も順調に周回する。がしかし、午後5時36分突然赤旗が出されレースが中断した。
何が原因なのかよくわからない状況で各ピットは騒然としている。しばらくするとサーキット全体で停電が発生し、レース運営ができないことからの赤旗中断だとわかった。
約1時間半中断し、午後7時05分から再びレース進行が行なわれ、7時45分に再スタートが切られた。
突然のアクシデント
再開後、凜太郎がファステストラップを9分01秒604に更新。午後9時29分カルロと交代。薄暮時でもっとも見づらい時間帯で日没は午後9時47分。カルロは周回ごとに、総合68位、67位と順位を上げ、60位まで上げたところでティムと交代。ティムは午後10時49分にピットアウトして行った。
夜間のティムは9分40秒ほどのラップタイムで順調に周回を重ね57位まで順位を上げた。しかし、午後11時20分ごろ緊急のピットインをした。なんと遅いマシンを抜きにかかったところ、左後ろに接触され、ティムはスピンを喫した。そしてフロントからガードレールにぶつかってしまったのだ。


ピットに戻り被害状況を確認した時の心境をチーフエンジニアの宮沢竜太は「これ、本当に直せるかな」と後に語っている。それほど被害状況は厳しいものだった。それでも全国のディーラーから選抜されたデメカ(ディーラーメカニック)達は直せることを前提に作業に取り掛かる。
フロント部はバンパーやラジエターを取り付けるフレーム自体が大きく変形しており、壊れた部品を交換するにも取り付けがままならないほどだ。メカニック達はハンマーを持ち、ひしゃげたフレームを直していく。左リヤの引き裂かれたタイヤと歪んだホイールが痛々しい。
5時間以上に及ぶ作業の末、なんとか元の姿に近い状態にまで復活させることができた。当然、チリは合わずボンネットピンの位置も大きくずれているものの、無理やりステーを曲げて止めている。ノーズ先端とボンネット先端部には大きな溝ができておりインタークーラーへの空気流入はスムーズではないことがわかる形状だ。それでもガムテームを巧みに使って空気が流れるように辻褄を合わせている。
長引くトラブル
深夜2時。エンジンがかかり、各部の点検をし、午前2時34分にティムが再びコースインをした。走り出してすぐにマシンが真っ直ぐ走らないことや、どこからか「ガラガラと音が出ている」ことを無線で伝えてきた。ショートカットできるグランプリコースだけを回って再びピットに戻した。



ティムからのコメントを元に、音の原因を絞り込んだ結果、プロペラシャフトとデファレンシャルギヤ、アーム類の交換をし、アライメントの取り直しという作業項目とした。
再びデメカたちの作業は始まり、背板もなく、床に直接寝転び、マシンの下に潜り込んでの作業だ。パドックのテント内にあるスペアパーツとピットとの往復をデメカたちはダッシュして繰り返す。アライメントも狂っており、修正作業が行なわれていく。

午前5時03分。孝太に代わってレースに復帰した。コースインをしてすぐに「これ大丈夫だと思う。このままオールドコースへ行ってもいいと思うよ」と無線が入る。29周目のクラッシュから復帰し30周目を終えた孝太は「足回りは問題ない、音も全然ないとは言わないけど、支障がある音ではないね。強いて言えば5速から4速、4速から3速へのシフトダウンの時に、少しだけショックが変わったけど問題ない。メカのみんなありがとう」と。
最高のチームだ
それから孝太は順調に周回を重ねていく。37周を終えて凜郎に変わる。朝6時36分。朝日が上り始める時刻になると眩しくて見にくいコーナーがあると無線で伝えてくるが、マシンは順調だという。凜太郎は「ここまで綺麗に治るとは思わなかった」とドライビング中の無線で伝えてくる。「凄いよ、みんな!」とチームに感謝を伝えている。

46周を終えてカルロが2回目のスティント入った。路面温度は上がりつつあり、タイヤは夜間用のソフトタイプからミディアムに変更。8時08分にピットアウトした。カルロもマシンの状態に心配はないと無線で伝え、メカニックを称えるコメントを送っている。
その後はティム、孝太、凜太郎、カルロという予定通りのルーティンでスティントを消化していく。午後2時16分、カルロのスティントになる。路面温度46度、気温28度で残り時間から逆算するとカルロでチェッカーを迎えるには周回数が予定より2〜3周多くなるためガス欠になる。
沢田監督はカルロのスティントを7周に減らして燃費を気にさせずにフルアタックすることを指示。最後はティムが3〜4ラップでチェッカーを受ける作戦に変更した。そして87周目、カルロが凜太郎の最初のスティントでマークした9分01秒604ファステストを塗り替える9分01秒322を出した。あの壊れたマシンを突貫修理で直したマシンでファステストを更新したのだ。
これにはチーム全員が安堵と感動と喜びが一気に押し寄せ、デメカ達はお互いに讃えあっていた。そしてラストスティントをティムがドライブをし、感動している自分の気持ちを無線で伝えながらチェッカーを受けたのだ。
ガレージでは歓喜の声と達成感、そして感動からの涙もあった。ドライバー達は口々に最高のチームだと賞賛を繰り返していた。

レース後沢田監督は「停電による赤旗やアクシデントもあり、修理のためにメカニックやスタッフが頑張ってくれて、再びコースに戻した時にまだ不具合が残ってて、という厳しい状況でしたけど、それもミックスして淡々と走れるようにできました。ドライバーから『最高のクルマになった』と言ってもらえたのが良かったです。それに、最後にカルロがファステストを出したことで感動ももらいました」とコメントしている。
一人のエンジニアが車両全体を、そしてチーム運営までも含めて俯瞰して見れるようになることを目指したニュル24h。参戦したチーム員たちは試練を経験し、大きく成長できた2025ニュル24hだったに違いない。
88号車、134台中総合76位。















